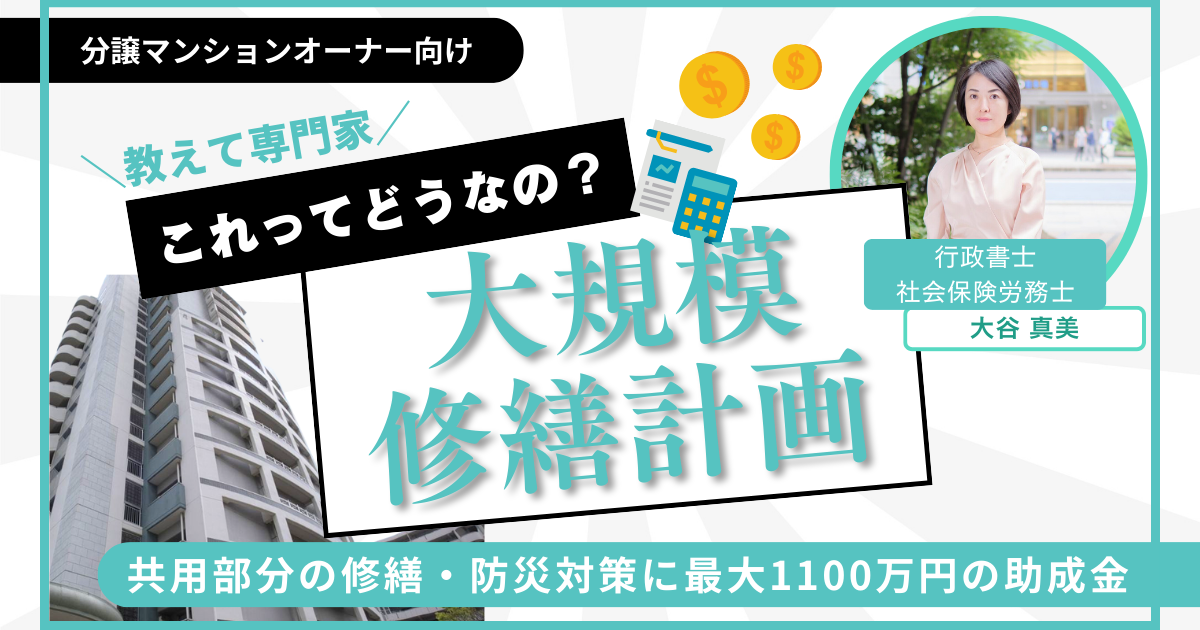日本には約2万件の補助金・助成金があると言われていますが、共有部分の改修工事を対象とした助成金があることはご存じでしょうか?
耐震、省エネ、バリアフリー化など建物に関する助成金の目的は様々で、実施主体も国、全国の地方自治体と多岐にわたりますが、今回は東京都中央区の「分譲マンション共用部分改修費用助成」に注目します。
参照:一般財団法人中央区都市整備公社「分譲マンション共用部分改修費用助成」

カノーゲル行政書士・社会保険労務士事務所
代表 行政書士・社会保険労務士
大谷 真美
松戸、虎ノ門、麻布十番の弁護士・行政書士事務所で合計15年勤務後
2020年9月に独立、補助金申請に特化したカノーゲル行政書士事務所開設
2023年11月、カノーゲル社会保険労務士事務所開設
これまで補助金・助成金をサポートした会社は300社以上
東京都中央区の築20年以上経過した分譲マンションはどのくらい?

2018年時点のデータによると、中央区内の分譲マンションは814棟、総戸数は58,346戸、平均築年数は21.5年とされています。このことから、築20年以上のマンションが相当数存在していると推察されます。
では、築20年以上のマンションはどのような課題を抱えているでしょうか?
参照:株式会社マンションデータサービス調べ(2018.1時点)「東京都の分譲マンション 地域別件数と戸数」
建物・設備の老朽化
外壁や屋上の劣化により、防水性能の低下やひび割れが発生しやすくなります。給排水管の腐食は漏水や水圧低下の原因となります。エレベーターや電気設備の故障があっても、部品の供給終了により修理が困難になる場合があります。
修繕積立金の不足
長期修繕計画の見直しが行われていない場合、将来的な大規模修繕に必要な資金が不足する恐れがあります。資材価格の高騰により、当初の積立金では賄えないケースが増えています。
建て替えの困難さ
建て替えには区分所有者全員の合意が必要であり、実現が難しい場合が多いです。全国的にも建て替えが実施されたマンションは全体の0.3%に過ぎません。
これらの課題解決の一助となるのが、東京都中央区の「分譲マンション共用部分改修費用助成」なのです。
ではまず概要を見ていきましょう。
東京都中央区「分譲マンション共用部分改修費用助成」の概要

1.実施主体
一般財団法人中央区都市整備公社
一般財団法人中央区都市整備公社は、地域社会の発展に寄与することを目的とし、昭和60年6月1日に設立されました。公社は、中央区だけでは実施が困難である都市整備事業について、弾力的かつ迅速に取り組んでいます(以後、「公社」と呼びます)。
2.対象となるマンション
- 東京都中央区内の分譲マンションである
- 建築時において、建築基準法その他関係法令に適合している
- 現に住宅として使用している
- 建築後、20 年以上経過している
大規模修繕工事の周期は一般的に12年~15年ですので、建築後20年以上経過というと、2回目以降の工事が対象となるケースが多いです。
3.対象となる工事(共用部分の改修工事のみ)
(1)修繕工事
①壁面の改修
②鉄部の塗装・取替え
③屋上・バルコニー・外部共用廊下の防水工事
④給排水管の更生・取替え
(2)防災対策工事
①受水槽・高架水槽の耐震型への取替え
②受水槽・高架水槽への感震器連動型止水弁の設置
③エレベーターへの地震時管制運転装置の設置
④昇降機耐震設計・施工指針(2014 年版)に基づくエレベーターへの耐震改修工事
⑤エレベーターへの戸開走行保護装置の設置
⑥遮煙性能を有したエレベーター出入口扉への改修
⑦防災備蓄倉庫の設置
⑧防火水槽の設置
⑨電気設備への浸水対策工事
中央区では、通常の老朽化対策(外壁や給排水管など)のほかに、高度な防災対策工事も助成対象です。地震や水害などの災害リスクに備える設備更新にも手厚い支援をしている点は、他自治体ではあまり見られません。
※(2)①、③、④については、中央区都市整備部建築課で行っている建築物耐震改修等助成の対象工事となる場合、本助成制度の対象にはなりません。
4.申請に必要な書類
- 分譲マンション共用部分改修費用助成申請書及び添付資料
- 改修工事実施についての管理組合総会の議決書の写し
- 改修に要する費用が計上されている管理組合予算書の写し(総会の議決を経ているもの)
- 管理組合の管理規約の写し
- 設計事務所の設計業務に対する見積書(契約書)の写し
- 建築士法の規定による登録を受けた建築士事務所(設計事務所)であることの証明書の写し
- 実際に改修工事を実施する業者の見積書(契約書)の写し(助成対象工事にかかる工事費が、その他の工事費と区別できる形式で記載されているもの
- 助成対象工事の内容がわかる改修工事の設計図書の写し
- 助成対象となる改修工事箇所の現況写真
- その他理事長が必要と認める書類
かなり大量の書類が必要になります。しかも工事着手後の申請は受理してもらえません。よって、これらの書類を揃えためにはどのくらいの期間が必要かを、大規模修繕工事の着工時期から逆算してスケジューリングする必要があります。
5.申請時期
助成対象工事の概ね2 か月前まで
工事着手後の申請は一切受け付けてもらえませんので、この期限は必ず守りましょう。
6.助成額
- 設計費用:助成対象部分にかかる設計費×3 分の2(住宅部分に限る)
- 工事費用:助成対象工事費×10%×3 分の2(住宅部分に限る)
他自治体では工事費のみが対象であることが多い中、中央区は設計と工事の2段階に分けて支援しています。多くの管理組合が負担に感じる初期の調査・設計段階にも助成が出るのは大きな特徴です。
※設計費用についての助成は、建築士法の規定による登録を受けた建築士事務所(設計事務所)によって行われた設計にかかるものに限ります。
7.助成限度額
- 設計費用:10 年間で100 万円(申請は2 回まで可)
- 工事費用:10 年間で1,000 万円(申請は2 回まで可)
例えば、設計費用600万円、工事費用1億5千万円の場合
助成額は、
設計費用:600万円×3分の2=400万円
工事費用:1億5千万円×10%×3 分の2=1,000万円
となりますが、上限がそれぞれ100万円、1,000万円なので、合計1,100万円の助成額となります。
制度によっては助成が一度きりという自治体もありますが、中央区では助成限度額の範囲内で10 年間に2 回まで申請可としています。大規模修繕や分割工事を計画的に行いたい管理組合にとって、中長期的な活用がしやすい制度になっています(同一年度の申請は1 回に限ります)。
8.申請の流れ
工事前
工事着手の2カ月前までに申請をします。
事業認定通知書を受理して、ようやく工事に着手できます。
工事後
完了報告書を提出します。
事前に支払ってもらえる「概算払い」は本制度ではありません。全て完了後の助成金交付となりますので、まずは自己資金で工事を実施する必要があります。
9.本制度の活用メリットとデメリット
東京都中央区だけの本制度、特に下記の3つのメリットに注目です。
メリット1:経済的負担の軽減
設計費は 最大100万円、工事費は 最大1,000万円まで助成されるため、自己負担を大幅に縮小し、無理のない計画的な改修が可能になります。
メリット2:建物寿命の延伸
外壁や屋上、給排水管、防水などの劣化対策は、早期に対応するほどコストを抑えられます。助成金を利用してタイミングよく工事を行えば、大規模な修理・補修を未然に防ぐことができ、長寿命化によりマンションの資産価値の維持・向上に繋がります。
メリット3:管理組合の合意形成が容易に
助成金があることで「自己負担が少なくて済むなら今のうちにやろう」という合意形成のきっかけになります。助成金は後払いなのでいったんは自己資金で実施する必要はありますが、助成があることで工事着工のハードルは下がり、その後の修繕計画の見通しも立てやすくなります。
一方、本制度を使うことのデメリットは何があるでしょうか。
デメリット1:事前申請が必要、申請前に着工すると対象外になる
この助成制度は「事前申請制」です。書類の提出・審査・承認が済む前に工事を始めてしまうと、全額が助成対象外になります。工事スケジュールとの調整が必要で、工事の開始時期が遅れるリスクがあります。
デメリット2:書類準備、手続きが煩雑
前述の通り申請には多くの書類や手続きが必要です。書類に不備があると、審査に時間がかかりますし差し戻されることもあります。
デメリット3:予算に上限がある
助成制度には毎年度ごとの予算枠があり、年度途中で枠が埋まる可能性があります。区の審査結果によっては、申請内容が一部減額されたり、不採択になる場合もあります。
最大の注意点は、準備不足で取り逃がすリスクです。計画初期から制度を意識し、助成制度に精通したプロ(設計者・工事会社・申請サポート業者)と連携することが必要です。対象マンション・工事・条件をよく確認し、無駄な見積・設計にならないよう調整の上、スケジュールを逆算して総会議案・住民説明会などを早めに実施しましょう。
まとめ

本制度は、単なる修繕支援を超え、「防災力強化」と「中長期的なマンション資産の保全」を制度設計に盛り込んだ、先進的かつ実用的なモデルです。他自治体の制度と比較しても、工事の幅広さ、設計支援、柔軟な運用の3点で非常に優れています。
この助成金を申請するにあたり、高度な事業計画の作成は必要ありません。マンション要件、工事要件などに合致して、決められたスケジュールに則って必要書類を提出できれば、採択の可能性は非常に高いです。
ただ助成制度というのは何でもそうですが、その年の予算の範囲内で決まり、将来いつまであるか保証されているものではありません。早めの検討・計画・申請が重要です。
東京都中央区の管理組合の皆さまは、この制度を積極的に活用し、快適で安全な住環境の維持に努めましょう。
本記事は2025年6月時点の情報に基づいています。 最新の制度内容や申請手続きについては、一般財団法人中央区都市整備公社のホームページをご確認下さい